床のごみや髪の毛、ほこり等が気になった時に、手軽に使えるような充電式のハンディ掃除機(ハンディクリーナー)を購入することになった。普段使いの掃除機以外に使う用途で、あまり重たくないのがいい。
サイズも値段もピンからキリまであって、ダイソンとかだと高性能で高価格。そんなに高級なものでなくてもいいという人も多いだろう。
でも、安物買いで出来の悪い製品を引いたら粗大ごみになる。コードレスのハンディクリーナーを買う時は何を基準に選べばいいのか、よくよく調べてみた。
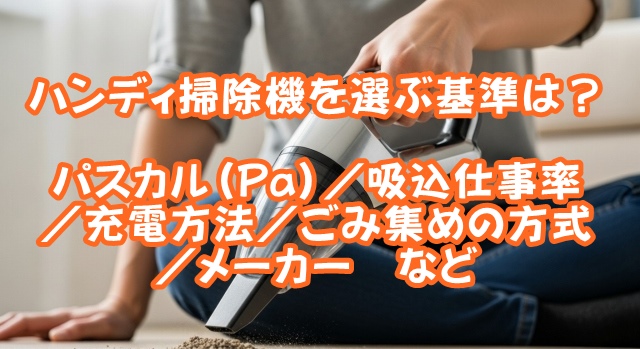
目次
掃除機の吸引力はどのように測定されるのか?

掃除機の吸引力は、主に以下の方法で測定される。
1. パスカル(Pa)による測定
掃除機の吸引力を示す最も一般的な単位は「パスカル(Pa)」。これは掃除機が持つ真空度を測定するもので、物を浮き上がらせる力を示す。特にロボット掃除機では、3,000Pa以上が吸引力の目安とされている。
2. 吸込仕事率(W)
吸込仕事率とは、掃除機が吸い込むことができる空気の量とその力を掛け合わせて算出される数値で、ワット(W)で表される。この測定は掃除機のヘッドを外した状態で行われ、特定の条件下での性能を示している。一般的に、吸込仕事率が400〜500W程度の掃除機は、十分な吸引力を持つとされている。
3. 水の持ち上げ能力(Water Lift)
水の持ち上げ能力は、掃除機がどれだけの高さまで水を持ち上げることができるかを測定する方法。この値は掃除機の吸引力を示す重要な指標であり、特に重いゴミを吸引する能力に関連している。水の持ち上げ能力は、通常インチまたはミリメートルで表される。ただしこれが明記されている製品は少ない。
4. エアワット(Air Watts)
エアワットとは掃除機の吸引力と風量を組み合わせた指標で、掃除機の全体的な性能を示すもの。エアワットは掃除機がどれだけ効率的に空気を移動させるかを示すため、吸引力の評価に役立つ。ただしこれが明記されている製品も少ない。
これらの測定方法は、掃除機の性能を理解するための重要な要素であり、購入時の参考になる。吸引力が高い掃除機は効果的にゴミを吸引できるため、掃除の効率が向上することは言うまでもない。
最近はほとんどの製品がパスカル(Pa)または吸込仕事率を明記しているので、この二つを指標にするのが無難。
購入の目安としての「Pa」

掃除機を選ぶ際、Paの数値は重要な指標となる。以下は、掃除機の種類別に推奨されるPaの目安。
ロボット掃除機:
2,000~3,000Pa: 基本的な掃除に適している。
4,000~6,000Pa: ペットの毛や混合フロアに適している。
7,000Pa以上: 深い掃除が必要なカーペットに最適。
ハンディクリーナー:
5,000~15,000Pa: 高い吸引力を求める場合は8,000Pa以上が望ましい。
一般的な掃除機:
10,000Pa以上: 強力な吸引力を持つモデルが多い。
最近は小型でも13000Paぐらいの吸引力は当たり前になってきている。ふつうに考えれば吸引力は弱いよりも強いほうがいいので、できるだけ数値の高いものを選びたいところ。
購入の目安としての「吸込仕事率」
掃除機の風量は吸引力に大きな影響を与える。風量とは一定時間内に掃除機が吸い込む空気の量を指し、通常は立方メートル毎分(m³/min)で表される。一方、吸引力は掃除機が物を引き寄せる力を示し、前述したようにパスカル(Pa)で表される。この二つの要素は、掃除機の性能を評価する上で非常に重要。
吸引力が強いだけでは掃除機が効果的にゴミを吸い込むことはできない。風量が不足していると、吸引力があってもゴミを掃除機内に運ぶことができず、実際の清掃能力が低下する。
吸引力と風量のバランスを示す指標として「吸込仕事率」がある。これは吸引力(Pa)と風量(m³/min)を掛け合わせたもので、掃除機がどれだけ効率的にゴミを吸い込むかを示す数値となる。単位はワット(W)。
吸込仕事率が高いほど、掃除機はより多くのゴミを効率的に吸引できる。一般的に、家庭用掃除機では400Wから500W程度の吸込仕事率が望ましいとされている。
製品によってはPaではなく吸込仕事率を表記しているものも増えている。吸込仕事率もPa同様に数値の高いほうがいいと思われる。
排気はどこから出る?

ハンディクリーナーを購入する際に、結構重要なポイントがもうひとつ。排気がどこから出るか。
モノによっては「使っていると吹き出し口から出る排気が顔に直接当たる」「横から勢いよく出るのでほこりが舞い上がる」といった口コミもちらほら。
特にPaや吸込仕事率の数値が高い製品を購入する場合、排気に関する口コミをちょっと注意して読んでみる必要がある。感じ方に個人差はあれど、使いにくい製品には必ずそういう口コミが書かれていたりするものだ。
充電方法は?

ハンディなので充電タイプがいい。でも充電式とひとえに言ってもさまざま。
最近よく目にするのが「USB充電」。スマホ用のやつで充電できますよ、というタイプの製品だ。ほとんどの場合、充電器は付属していない。また、充電する際にいちいちケーブルを抜き差しする必要がある。
ACアダプターを使って充電するタイプも多い。一昔前はこれが主流だったような気がする。プラグの抜き差しの手間はUSBと同じ。
使い勝手が最も楽なのは、充電スタンド(クレイドル)に乗せて充電するタイプ。置くだけで充電できるので、いちいちプラグを抜き差しするわずらわしさがない。
バッテリーがカートリッジ式で、別に専用充電器が用意されているタイプもある。この手の製品はバッテリーだけでも別途購入できるため、長く使うのには向いている。
なお、充電タイプと銘打っていても、よく見ると充電乾電池を入れて使う製品もある。交換が効かない内臓バッテリータイプと違って充電乾電池を交換するだけで済むため、本体寿命が長いのがメリットだが、それが充電タイプと言えるのかは疑問。
ごみ集めの方式について

ハンディクリーナーのごみ集め方式もいくつか種類がある。
紙パック式: 吸い込んだゴミを専用の紙パックに集める方式。ゴミが紙パックに溜まり、空気はパックを通過して排出される。この方式はゴミ捨てが簡単で、ホコリが舞い上がりにくいという利点があるが、紙パックの交換が必要で、消耗品としてのコストがかかり続ける。(1枚あたり50円ほど)
サイクロン式: ゴミを高速回転させて遠心力で分離し、ダストボックスに集める方式。紙パックを使用せず、吸引力が落ちにくいのが特徴。定期的にゴミを捨てる必要があるが、ほとんどの場合ダストボックスが半透明になっているので見た目でわかりやすい。
カプセル式: サイクロン式に似ているが、ゴミをフィルターで分離してカプセルに集める方式。カプセルは取り外し可能で、ゴミ捨てが比較的簡単。フィルターの手入れ(清掃)が別途必要。
製造メーカーで選ぶのもあり

安心できる製造メーカーなら、多少のことがあっても気分的に許容できる。お気に入りのブランドがあるなら、それを選ぶのが得策かもしれない。
Amazonなどの通販、ホームセンターや量販店などの実店舗にはいろいろなメーカーの製品が並べられている。名前はよく目にするけれど、どこのメーカーなのかわからなかったりする。
SmartAI、Toauo、Ainova、YFYunDlldu、Yutesiri、Linkifly、HOTO、LEACCOHOME、Fanttik、Iosare、Fanttik、LEKGAVD、Haier、Uowind、ZAFRO、MOVA、DREAME(ドリーミー)、BOLYDOOM、Roborock、Xiaomi、ZAFRO、COMHOMA、Bivarkは中国。
Zharsnenは香港。
RAYCOPは韓国。
Shark(SharkNinja)はアメリカ。
ツインバード、Fukai、HiKOKI、エペイオス(Epeios)、シロカ(siroca)、サンカ(Sanka)、recolteは日本のメーカー。アクア(AQUA)は日本のメーカーだが実際には中国のハイアール傘下にある。オーム(OHM)、Orage(オラージュ)、BRUNOは日本のメーカーだが製造は中国。
日本のメーカーでも製造拠点が中国である場合も少なくない。国内で品質管理をしていれば信頼性も高いが、そこまではわからない。
Mottinhill、Dantee、BeeTool、Hearten、LNSOOは未確認(不明)。
中には本拠地不明なメーカーというのがけっこうある。低価格な製品が多いが、サポート等を考えると若干不安が残る。
評価の高い製品は?
ハンディクリーナーの価格帯は広く、安いものは2000円台から、高くなると5万円ぐらいまである。価格の高いものほど評価が安定している傾向にあるので、予算が許すのであれば安物買いをしない方が後悔しなくて済む。
以下は、Amazonや楽天市場などの通販サイトで比較的口コミ評価が高いハンディクリーナーのメーカー5社。
ダイソン(Dyson): サイクロン式掃除機の技術を活かし、強力な吸引力と静音性が特徴。特に「V7シリーズ」は人気がある。
マキタ(Makita): 日本の電動工具メーカーで、ハンディクリーナーも軽量で吸引力が高く、プロ仕様からリーズナブルなモデルまで幅広く展開している。
シャーク(Shark): スタイリッシュなデザインとパワフルな吸引力が特徴のメーカー。特に「EVOPOWER」シリーズが人気。
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA): コストパフォーマンスに優れた製品を提供し、手頃な価格で高性能なハンディクリーナーを展開している。
ツインバード(Twinbird): シンプルで使いやすく、安価で手に入るハンディクリーナーを提供。技術力の高さも魅力。
これらのメーカーは、口コミ評価が高く、信頼性のある製品を提供している。ダイソンはイギリス、シャークはアメリカ。マキタ、アイリスオーヤマ、ツインバードは国内メーカー。
まとめ
吸込仕事率は掃除機の選定において重要な指標だが、実際の使用環境や掃除機の設計、ブラシの種類なども考慮することが大切。高い吸込仕事率を持つ掃除機が必ずしも優れた性能を持つとは限らないため、総合的な判断が求められる。
数あるメーカー・製品から一品だけを選ぶのはなかなかに難しい作業だが、じっくり選ばないと後悔につながる。安物やタイムセールに飛びつくのでなく、ある程度上の価格帯で選んだ方が確率的に当たりを引きやすくなると思われる。
